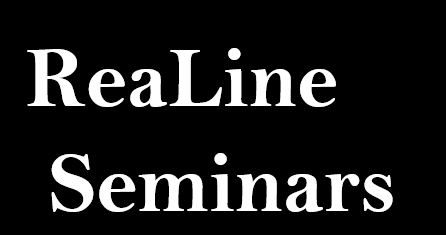頸部評価の奥深さを学ぶ - JHS2025-07セミナーレポート
頸部の評価と治療に悩む理学療法士の皆さん、頸部の複雑な構造と機能を理解し、的確な診断と効果的な治療を行うための知識を深めたいと思っていませんか?過去に開催されたJHS2025-07セミナーでは、こうした悩みを解決するための貴重な学びが提供されました。
解剖学から臨床応用まで:頸部診断の総合的なアプローチ
セミナーでは、頸部の解剖学的特徴からスタートし、特に頸椎の複雑な構造とその機能について詳しく解説がありました。臨床で重要なポイントとして、自動運動検査の手順や画像診断(レントゲン・MRI)の読み方、アライメント評価の技術が取り上げられました。フォワードヘッドポスチャーが及ぼす影響や上部交差症候群の評価方法についても詳しく説明され、参加者の皆さんは熱心にメモを取っていました。
臨床で見過ごせない「椎骨動脈」のリスク管理
特に印象的だったのは、椎骨動脈障害に関する注意喚起です。頸部の理学療法を行う際、血管系の問題を見逃すと脳卒中や脳梗塞のリスクにつながる可能性があるとのことでした。講師の先生は「臨床では通常、椎骨動脈テストは実施しない」と繰り返し強調され、その代わりにどのような評価をすべきかを具体的に説明されました。
神経根症診断の実践的アプローチ
後半は頸椎神経根症の評価に焦点が当てられました。スパーリングテストやジャクソンテスト、ショルダーアブダクションリリーフサインなど、様々な検査法のデモンストレーションがありました。「教科書的な知識だけでは診断が難しい症例がある」という指摘もあり、皮膚分節や筋力低下のパターンが典型的でない場合、超音波検査による神経根の評価が有効とのことでした。
セミナーの学びと次のステップ
セミナー終了時には、次の課題が参加者全員に提示されました:
- 頸部自動運動検査の復習と実践
- 「スマホ首」の症状と予防法の調査
- 頸部痛の急性・慢性の違いと対応方法の学習
- 頸椎のアラインメント評価の実践確認
特に、頸部の神経根症状評価では「複数の検査を組み合わせて総合判断する」ことが重要と何度も強調されました。次回は講師による頸部評価・治療の実践デモンストレーションが行われる予定で、参加者の期待が高まっています。
頸部の評価と治療に悩む理学療法士の皆さん、この機会にぜひセミナーに参加して、さらなる知識と技術を習得してください。今すぐ行動して、臨床でのスキルアップを目指しましょう。
セミナーの詳細を見る