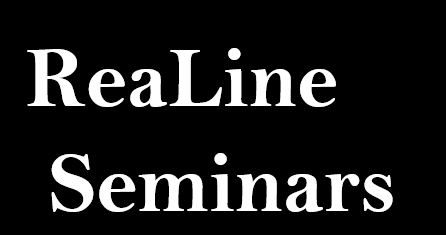セミナー:
250806 JHS2025第09回 肩甲胸郭関節:解剖学・運動学・バイオメカニクス
内容:【250806 JHS2025第09回 肩甲胸郭関節:解剖学・運動学・バイオメカニクス】セミナー概要と学びのポイント
先日開催された「250806 JHS2025第09回 肩甲胸郭関節:解剖学・運動学・バイオメカニクス」セミナーでは、肩甲胸郭関節の複雑な構造と機能に焦点を当て、理学療法士やトレーナー、柔道整復師、産前・産後ケア従事者、助産師など多様な専門職が集い、その最新知見と実践的アプローチを学びました。肩甲骨の運動学、バイオメカニクス、神経学的連携に関して深掘りし、肩の異常運動が単なる症状ではなく結果的な代償であるという視点が特に印象的な内容でした。
【肩甲胸郭関節セミナーの特長と強み】
本セミナーの最大の特長は、肩甲骨を単なる骨格のパーツとしてではなく、上肢運動の“土台”と捉え、胸郭や神経系との連携を包括的に評価・理解できる点にあります。肩甲上腕リズムについては、伝統的な2:1比率だけでなく、多様なリズムや年齢、利き手により左右される動態を詳細に解説。さらに、肩鎖関節・胸鎖関節の機能的役割や肩甲胸郭リズム、滑液包、神経走行の深い理解も促します。
実践面では、肩甲骨の異常運動が結果であるという視点から、介入の優先順位を見直す視座が示され、運動療法設計における根拠を強固にします。腱板損傷患者に対しては、肩甲骨後傾を促す重要性、ウイングイングのメカニズムが前鋸筋以外の筋肉も含むことなど、多角的で実用的な知識も豊富です。
内容は最新の論文や臨床研究を参照しつつ、多様な測定方法や姿勢変化による誤差の存在にも言及。受講者が自ら文献を批判的に読解し、適切に臨床応用できるよう指導する点でも優れています。
【受講者の生の声:充実した学びと今後の期待】
受講者からは次のような感想が寄せられています。
-
受講者1
今回のセミナーで肩甲骨の運動学・バイオメカニクスを学び、肩甲骨の異常運動が結果的代償である視点や胸郭・神経との連動性の評価が重要と理解しました。運動療法設計の根拠も深まりました。
★5 -
受講者2
肩甲骨が上肢運動の土台である視点から、筋肉の協調や代償運動、神経障害まで整理され実践的でした。肩甲骨の異常は結果である点は介入優先順位の再考につながりました。
★5 -
受講者3
長胸神経損傷に鍼や注射が関与する可能性について詳しく知りたかったため、鍼灸師として安全なアプローチについて今後の講義を希望します。
★3 -
受講者4
肩甲上腕リズムは代表的な2:1だけでなく多様で、年齢や利き手による左右差もあり、肩甲骨周囲の関節包が多いことを知りました。
★3 -
受講者5
翼状肩甲は菱形筋由来の場合は肩甲背神経麻痺が原因で神経は深部にありエントラップメントは少なく、前鋸筋由来は長胸神経麻痺で神経は表層にありエントラップメントを起こしやすいと理解しました。
★4 -
受講者6
肩甲骨の運動や肩甲胸郭リズム、胸鎖・肩鎖関節の機能、滑液包や神経を深堀りし、前額面だけでは判断できないこともあると学びました。
★5 -
受講者7
教科書上の名称や肩甲骨の位置関係、支配神経を再確認でき、肩甲上腕リズムが2:1に限らず場面や年齢で異なること、また滑液包やウイングイングの因子が多様であることに驚きました。
★5 -
受講者8
肩甲上腕リズムが姿勢や脊柱後弯、年齢で変化し、腱板損傷では肩甲骨の後傾を促す必要があり、ウイングイングは前鋸筋以外の筋肉の影響もあることがわかりました。
★5 -
受講者9
肩甲上腕リズムは測定方法で誤差があり、健常者と高齢者や腱板損傷、円背姿勢とも関連しているので、論文を読む際は年齢など対象条件に注意が必要だと理解しました。
★5 -
受講者10
新しいスライドが多かったためハンドアウトを確認し、巻き肩や円背による肩甲上腕関節の動きの違いを旧知と違うことを意識しながら理解を深めたいです。
★5
これらの声から見えることは、肩甲胸郭関節の複雑な運動パターンや神経支配を、実践的かつ最新エビデンスに基づいて体系的に理解できたという点です。肩甲骨の異常運動は単なる問題点ではなく、体幹や姿勢変化を含めた全身の連動的な結果であること、介入の優先順位の再考につながるという知見は多くの受講者に大変好評でした。
一方で、長胸神経損傷に伴う鍼や注射などの間接的リスク、安全な施術方法への関心も明示され、今後の講義へのリクエストも寄せられていることから、専門性を深める継続的な学びの場としての期待も伺えます。
【まとめ:専門性と実践力を高める最適なセミナー】
本セミナーは、肩甲胸郭関節の解剖学・運動学・バイオメカニクスの理解を深めるだけでなく、臨床応用を重視している点が非常に価値ある特徴です。肩関節治療の基盤となる肩甲骨の機能評価や介入優先順位の見極めに困っている理学療法士、トレーナー、柔道整復師、さらには産前・産後ケアや助産分野の専門職にとっても、大変有益な内容です。
豊富なスライドや手厚いハンドアウトが学びをサポートし、受講料も内容に対して割安であるとの声が多数。最新の研究知見を現場にいち早く反映させたい方に特におすすめいたします。
【今後のセミナー開催と申し込みリンクのご案内】
この他にも専門性を高める各種セミナーが多数開催されています。ぜひご自身の専門分野に合ったコースで継続的なスキルアップを目指してください。
▶組織間リリース(ISR)
東京、鹿児島で開催。鹿児島は全4回セット申込まだ可能
https://seminar.realine.org/collections/isr_advance
▶ウィメンズヘルス理学療法(WHPT)
東京、京都で全4回開催
https://seminar.realine.org/collections/whpt
▶クリニカルスポーツ理学療法(CSPT)
鹿児島で第1回開催(全4回)
https://seminar.realine.org/collections/cspt
▶産前・産後ケア勉強会
東京・大阪・京都・鹿児島・福岡・岡山・札幌開催
https://seminar.realine.org/collections/pregnancycare
専門家としての知見を深め、患者様やクライアントにより質の高いケアを提供するために、本セミナーへの参加をぜひご検討ください。
■実技セミナーを探す⇓
https://seminar.realine.org/pages/hands-on
■オンラインセミナー(ライブ、オンデマンド)を探す⇓
https://seminar.realine.org/pages/online